
一食目
『バナナの丸かじり』東海林 さだお(朝日新聞出版)
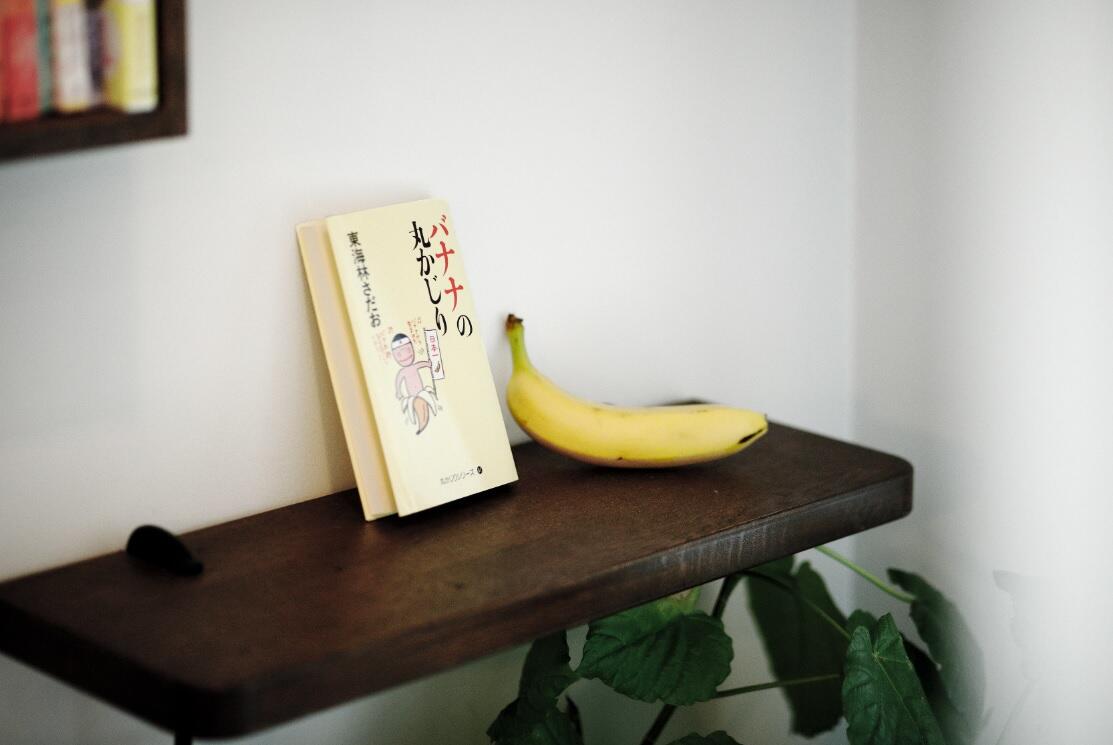
世の中には、話を進めない才能をもった人間がいる。
テレビのバラエティ番組を見ていると、話が全く進んでいないのにも関わらず、場が盛り上がり笑いが起こっている場合がある。そんな時は大体この「話を進めない才能」を持った人間が話を停滞させながらも、面白おかしく話題を展開させている。
かつて昼の国民的バラエティ番組のパーソナリティを務めていたあの人も、まさにこのタイプだった(今は某公共放送でブラブラ歩いているあの人です)。個人的には話題が進まないことにイライラすることもあるが、世間一般の多くの人はどうやらそこまで心が狭くないらしい。
今回、紹介する「丸かじりシリーズ」(連載時の原題は『あれも食いたいこれも食いたい』)の筆者である東海林さだおも、間違いなくこの「話を進めない才能」をもった一人だろう。毎回一つの食材にテーマを絞り一本のエッセイに仕上げるこのシリーズは、今年で連載32年目に入る人気企画である。
筆者の東海林さだおは、この32年間、毎回、何らかの食材についてエッセイを書き続けてきたわけだが、連載が長期にわたると同じ食材がテーマに登ることもある。その場合、当然ながら、同じテーマであっても以前の物とは別の切り口でエッセイを書くことになる。そこで発揮されるのが例の話を前に進めない才能だ。
東海林さだおは、決して一つの食材について、あらゆる事については語らない。一つの食材からほんの些細な事を見つけだし、その事についてだけを延々と語る。それゆえ、一つの食材だけで何本もエッセイを書くことが出来る。
ただ、これは並大抵のことではない。仕事で書くのだから面白くなくてはいけない。一つの食材の些細な事に目をつけ、それだけで延々と面白おかしく読者を満足させる話を書くことが出来るのは、まさに才能以外の何物でもない。
最新作『バナナの丸かじり』でも、東海林さだおはグミの弾力について語り、カマボコの厚みについて語り、ポテトチップスをポテチと呼ぶことについて語り、鯛焼きの形について語り、食べ終われば何も残らないアイス最中を称賛し、歯は時代遅れであると指摘し、バナナの皮で人間は本当に転ぶのかを検証する。
たわいないと言ってしまえばそれまでだが、そもそもエッセイとはそういうものだ。たわいない話題の中から、自分と自分以外の人間の間にある差異を愉しむのが、エッセイを読むことの醍醐味である。その中でも、話を進めない才能を持った人間によって書かれたエッセイは最上の物ではないだろうか。
何故なら話を進めない才能の本質は、人が注目しないような事実に気付く力であり、旺盛な好奇心であり、優れた観察力にあるからだ。東海林さだおのエッセイが30年の歳月を越え、未だ多くの読者に支持され続けていることがなによりもその証左ではないだろうか。
さて、同じく作家によって書かれた食のエッセイとして時代小説の大家、池波正太郎の筆による『散歩のとき何か食べたくなって』(新潮社)も勧めておく。こちらは筆者の確かな哲学に裏打ちされたエッセイが、古き良き時代の店と客双方の矜持を伝えてくれる良著である。是非、一読されることをお勧めする。
撮影/伊藤 信 構成/吉田 志帆