
日本は相当な韓国ブームである。映画やドラマには韓国の風景が氾濫している。しかし、韓国の料理はもっと前から流行っていた。コチュジャンや唐辛子の辛さに代表される韓国の味はますます日本に浸透してきている。辛い味は好きになるとやめられない。なぜかと問われても返事に窮するが、いったん好きになると、辛くないものはもの足りない。
昭和50年代後半のいわゆる第1次唐辛子ブームの頃は、まだ、辛味は日本国民の舌にそれほど浸透してはいなかった。珍しいものを食べるように辛味を味わった。今は違う。いつの間にか日本にも韓国料理の店が増えた。基本となるダシのおいしさが共通しているので、日本人にも違和感はない。辛さだけが障害だった。それも無くなってきている。

韓国の大衆料理店は、ホテルのレストランと違って地元のヒトで満員である。値段も断然安い。おまけに、辛さは10倍辛い。頭まで赤くなるほど辛くなくてはソウルっ子は満足できない。しかし、ソウルの料理は韓国の地方に比べるとまだ辛さが穏やかなのだそうだ。韓国のヒトは辛味がないとどうにも満足できないようだ。日本料理すなわち「日式」は味は良いが辛味がもの足りないと地元の人たちは言う。
唐辛子の辛味の主成分はカプサイシンである。化学的にはバニラと似た構造をしている。バニラに長い尻尾が付いたものに近い。かつて、カプサイシンをネズミの小腸に投与する実験を行ったことがあるが、ネズミのリンパ液にバニラの甘い匂いがぷんぷんした。カプサイシンが小腸で分解され、さらに構造が少し変化してバニラになったのである。

唐辛子がなぜ辛いのかは、科学的にはよくわかっていなかった。唐辛子の辛さは痛覚である。それがわかったのもそんな昔ではない。皮膚にカプサイシンを塗ると痛い。口の中に痛み刺激を与えると辛いと感じるのである。
しかし、疑問も残る。口の中を怪我したら痛い。怪我の痛みをなぜ辛いと感じないのか。熱いお湯を飲むと熱いだけで辛いとは感じない。どうやら、辛いという感覚は痛いに加えてもう少し複雑な要因が加味されているようである。しかし、実体はよくわかっていない。
トウガラシの辛味であるカプサイシンが口の中を刺激する仕組みについては、かなり解明が進んできた。カプサイシンの口の中での標的はなんと熱さを感じる温度受容体だったのである。これが全身に分布する。43度以上の温度によって痛いと感じる。唐辛子が作用すると43度以上で刺激されるはずの受容体が体温でも熱く感じる。
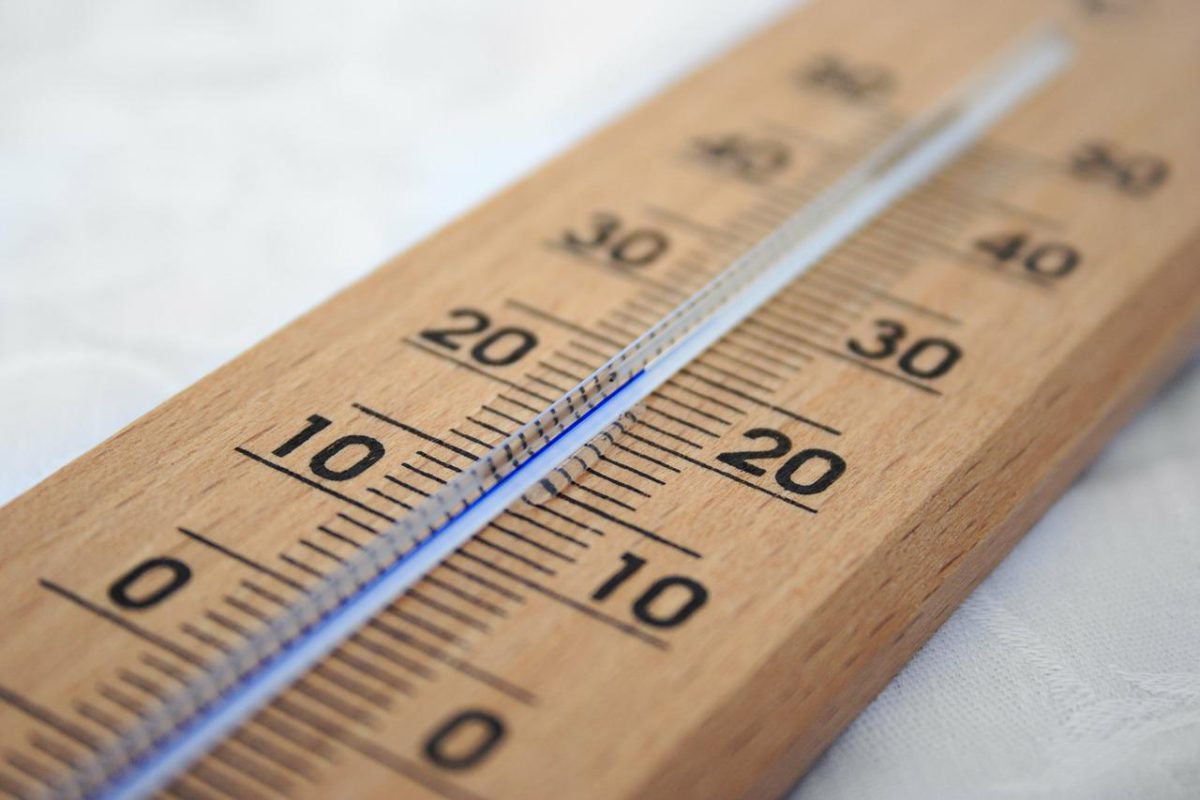
つまり、トウガラシが刺激した部位は体温が熱い。トウガラシの辛さはこのためなのである。英語では辛味をホットと言う。科学的にもホットである。科学者よりも先になぜわかったのだろう。
韓国でもタイでも、子供のうちはやはり辛い味が苦手なのだそうだ。辛味の好みは遺伝しないのだ。親が子供を訓練する。徐々に辛味に慣れさせる。10才を過ぎる頃には平気になるそうだ。自国の文化を守るための努力である。

辛い味はいつの間にかやみつきになる。そしてどんどんエスカレートする。辛い味にはやめられなくなる効果があるに違いない。そこで、ネズミにカプサイシンの辛い溶液を毎日与える実験をした。タイや韓国の人の好みに近いネズミができあがると期待したのだ。

はじめはネズミは辛い溶液を嫌がった。最初だから仕方がない。ところが、数日たっても同様である。数ヶ月たってもいっこうに辛い味を好きにならないのである。どうやら辛い味溶液だけを与えても好きにならないようだ。
では、韓国やタイの人々があれほど辛い料理を好むのはなぜか。もっと長い年月が必要なのだろうか。タイの大学の先生に辛い料理をなぜ好きなったのかと聞いたことがある。先方は驚いた顔をして、
「辛さが欲しいのではありません。辛味や甘味やうま味のよく利いた料理が美味しいのです」
なるほど、辛い味そのものが好きなのではなくて、おいしい料理に辛い味がついているから辛い味が好きなのだ。料理のおいしさと辛い味をセットで好きになっている。しかも、いったんセットで好きになったら、辛い味がないと料理はもの足りない。後戻りもできない。そんな仕組みのようだ。
辛味が温度受容体だと言ったが、ミントの冷たさもよく似た温度受容体への刺激である。温度受容体にはたくさんの種類がある。こちらは、冷たい温度に刺激されて冷たさを感じる低温受容体である。偶然にミントが低温受容体を刺激する。だからミントはクールなのだ。

口の中でホットだったりクールだったりする食材の多くは、温度受容体を刺激するものである。マスタードやシナモンをはじめ多くの香辛料も然り。温度感覚さえも、人間はおいしさとしてとらえるのである。
出典「逓信協会雑誌」(平成18年7月号通巻1142号)