
2023年2月に行われた、京都の料理人と研究者が1年間の研究成果を発表するシンポジウム。今回は「今、もっとも贅沢な京料理」をテーマに、“今の時代に何をもって贅沢と定義するか”の考察が繰り広げられました。
<前編>につづき、シンポジウムの様子をレポートします。
2つめのプレゼンテーションで登場したのは「鴨まんじゅう」。「たん熊北店」三代目主人・栗栖 正博 氏は「日本料理の“まんじゅう”の中でも、元祖的な存在」と語ります。男爵いも、百合根、つくねいもを蒸し、木べらを使ってキメの細かい網で裏ごしします。これらを合わせ、甘辛く炊いた鴨ミンチを中に入れて丸め、叩きつぶした手焼きあられをまぶします。油で揚げたら、湯をかけて油抜きをし、さらに蒸して、一番だしで作るあんをかけて完成です。

「味わいの最大ポイントは、京都・橘屋のあられ。干した餅を炭火で手焼きするあられは、ここでしか求めることができません。あられの技術も次世代に継承したいという想いでお出ししました」。

龍谷大学 食と農の総合研究所「食の嗜好研究センター」センター長であり、農学部 食品栄養学科 山崎英恵 教授が「外注するのも、じつは大切なのですね」と聞くと、「料理屋は、人と人との関係性で成り立っています。橘屋の主人は親友でもありますし、湯葉や生麩も信頼しているお店から仕入れています」と、栗栖氏。
顔が見える生産者と信頼関係を築くことも、京料理の大切な要素のひとつ。ひいては地域連携、地域振興につながっている点も見逃せません。

続いては、「平等院表参道 竹林」主人・下口 英樹氏による「鰻の松皮湯葉」。そもそもは、鰻を短冊に切り、薄く切った豆腐で巻いて焼き目をつけた「鰻の松皮豆腐」がもとになっています。
「鰻の松皮豆腐は昔、父親と一緒に厨房に立っていた料理人が作っていたという料理です。料理人仲間で知っている人はいませんでしたが、『萬亀楼』の小西さんに、宮中料理にのっとった有職料理には松皮料理があると教えてもらいました」。
しかし柔らかい豆腐で巻くと鰻の量が少なくなり、リッチ感を出すことが難しいことがわかりました。そこで豆腐の代わりに崩れにくい湯葉を使うことで、鰻の量を増やすことができたそうです。また、焼き目で「松」、合わせたタケノコで「竹」、金時人参で「梅」と、松竹梅を表現しています。

「京都の食文化の中で、長らくテーマだったのは、京都ならではの素材にどうやって手をかけて料理として仕立てるかということ。京都の代表的な素材として豆腐・湯葉・川魚(鰻)の3つが挙げられますが、現代において豆腐は庶民的になり過ぎています。また鰻は、鰻専門店のうな重以外にあまり食べられていません」と、下口氏。
家庭でも食される豆腐ではなく湯葉、そして鰻専門店では食べられない手法の鰻料理を提案したのは、そのような背景がありました。

「京料理 木乃婦」三代目主人・髙橋 拓児氏は「あなたは、赤飯を誤解している」と、世間一般の「赤飯」に疑問を提示しました。「そもそも赤飯が赤いのは、疫病を避けてめでたさを呼ぶため。うちの赤飯はしっかり赤い」と、髙橋氏。「日本料理のキーワードのひとつが、時間をかけるということ」とも語ります。

小豆を水から茹で、沸いたら湯を捨てて渋みを取ります。色のにごりを防ぐため割れた小豆を箸で取り除く作業も必須だそうです。さらにステンレスの鍋で5時間かけてさらに炊きますが、ひしゃくですくって氷水に当てながら酸化を進めて赤みを強めます。
もち米は、「白蒸し」という技法をアレンジし、赤く染まった煮汁と少量の小豆で蒸し上げ、その後で茹で小豆を加えます。

鮮やかなワインレッド色の赤飯は、見た目がきれいなだけではありません。色がにごっているとえぐみや渋みが感じられてしまうそうです。「ほんまもん」の赤飯のプレゼンテーションには、上質の小豆を使うこと、鍋につきっきりで丁寧に仕上げること、酸化という化学反応をうまく使うことなど、さまざまな工夫が詰まっていました。
最後のプレゼンテーションは、「贅沢とは真逆の3品」と、龍谷大学 名誉教授の伏木 亨氏。

「りゅうひ昆布巻」は「京料理 清和荘」三代目主人・竹中 徹男氏の作です。竹中氏は修業先から戻ってから、昆布巻は作ったことがありませんでした。先代が昭和40年代につけていた献立帳で、9月のメニューとして『鮎の昆布巻』のレシピを見つけたことをきっかけに、昆布巻に着目しました。
江戸時代から明治にかけ、大阪と北海道を結んだ「北前船」により、真昆布が京都に運ばれてきました。昆布は『喜ぶ』とかけ、縁起が良い食べ物としておせち料理に入れられるようになります。
「りゅうひ昆布巻」は、完成まで3日かかります。
大きめの子持ち鮎に串を打って両面を焼き、冷蔵庫でひと晩休ませ、翌日、ほうじ茶で5時間湯がきながら余分なアクや脂をすくい取り、流水で1時間さらして表面のぬめりや汚れを取り去り、半日休ませて水を切ります。昆布で子持ち鮎を巻き、水と清酒で炊いたのちに砂糖、みりん、薄口醤油で調味して炊き上げ、冷蔵庫でひと晩寝かせて、ようやくできあがりです。
子持ち鮎のしっとりと柔らかな食感、わずかな酸味、品のあるあと味が一体となった一品。「りゅうひ昆布巻は、鮎を美味しく食べるための料理」と、竹中氏。手間と時間がかかるうえ、華美ではない料理ですが、現代であまり作られない料理を再構築し、後世に伝えるものとしました。

昭和初期に撮影された「美濃吉」のお座敷での写真で見つけた「うなぎの炊いたん」を再現したのは、「京懐石 美濃吉 本店 竹茂楼」調理総支配人・佐竹 洋治氏。

炊いたうなぎに添えたのは、うなぎの骨と頭を低温で揚げ煮してペースト状にしたものと、肝を甘辛く炊いてペースト状にしたものを胡麻豆腐に入れて練り上げて火を通した、濃厚豆腐です。うなぎの骨と頭の揚げ煮は、昭和初期の「美濃吉」でも用いられた手法だそうです。
うなぎは、頭、骨、肝と捨てるところのない食材です。昔から京料理の世界ではフードロス削減の精神が根付いており、SDGsという言葉がない時代から「食材を余すことなく使う」ことが実践されてきました。佐竹氏がうなぎを再考した理由は、近年、世界的に施策が進んでいる食品ロス問題の解決やSDGsの実践に向けた試みでもありました。

最後に登場したのは「おから」です。「京都の商家では、食材を最後まで使い切り始末することを良しとしています。月末には、財布がカラになる月末でもお金が入る(=炒る)ようにという縁起をかつぎ、おからを食べていたものです」と、「一子相伝なかむら」六代目主人・中村 元計氏。

おからは庶民が安く食べることができる料理です。「昔から伝わる日本料理には、必然性と合理性がある。そこに、現代の調理技術とトレンドを加えたものがもっとも贅沢な料理ではないか」と、中村氏は語ります。
おからは豆腐を作る際に出る絞りカスですが、今回は老舗「湯葉半」で、大豆を蒸して石臼でつぶしたものを使用。やや荒めのため食べたときに粒が舌に当たり、食べ進めるごとに食感の変化が楽しめるそうです。具材は、牛肉、糸こんにゃく、にんじん、干し椎茸、蓮根、青ネギ、ゴボウ、しめじまたはえのき、油揚げの9種類です。
「牛肉は、前日のすき焼きの残りものでいい。油揚げと、仕上げにかけるごま油は嗜好性を高める効果があります」。
父親譲りのレシピには、昆布やかつお節でとったダシを使用せず、干し椎茸、ゴボウ、しめじまたはえのきから出るダシで旨みを表現しています。
NPO法人日本料理アカデミーでは、「本物のダシを味わう事は教養である」という事業を京都大学でおこなっており、ダシの可能性を再発見できる一品ともなりました。

今回のテーマ「今、もっとも贅沢な京料理」ではいずれも、昔から親しまれてきた食材を、京料理の職人技で手間と時間をかけて“贅沢な料理”に昇華させていました。
山崎教授は「現代は、高価な食材が“贅沢”とされています。しかし、これから残すべきは、伝統の技や先代からの知恵が詰まったプロセスだと知ることができたのは大きな収穫でした」と、研究の成果を評しました。

「菊乃井」の主人・村田 吉弘氏は「プレゼンテーションを通し、なぜ京料理が登録無形文化財に登録されたかの理由がおわかりいただけたと思います。私たち料理人は、長い歴史の中で伝承されてきた文化を次世代に継承する役割を担っています。また、料理文化は食べ手がいないと成立しません。京料理は記念日など特別な日に召し上がる方も多いでしょうが、だからといって特別すぎて食べられないという状況になってもアカンと思います。誰もが日本の食の真髄を楽しめるようにするのが、私たち料理アカデミーの役割です。今回は、食べ手であるみなさまにも料理人にも、料理や文化への理解を深めていただけるきっかけとなったのではないでしょうか。龍谷大学の先生方、配膳を担当してくれた学生たちや若い料理人たち、スタッフのみなさまに多大なる感謝をいたします」と、シンポジウムの成功とともに、次世代に向けた料理文化への発展を願う言葉をいただきました。
龍谷大学とNPO法人料理アカデミーによるシンポジウムは今後も開催される予定です。一般参加も可能ですので(要申込)、料理や食文化に興味のある方は、ぜひ参加して日本料理への知見を深めてみてくださいね。

2023.03.22
「今、もっとも贅沢な京料理」〜龍谷大学×日本料理アカデミー シンポジウム報告<前編>

2021.03.23
「日本料理:アジェンダ2021」龍谷大学×日本料理アカデミー研究成果報告会

2020.03.09
日本料理における品位とは? 龍谷大学×日本料理アカデミー シンポジウム報告 vol.1
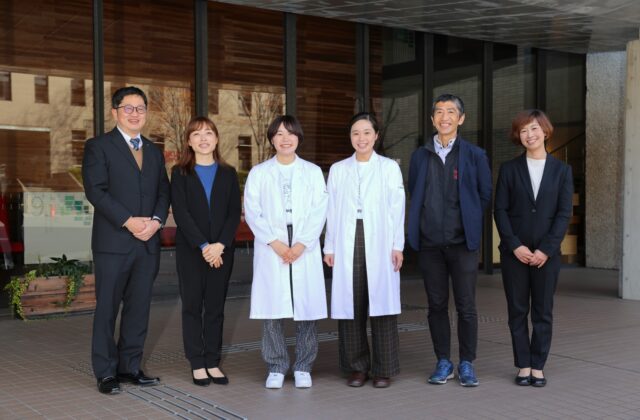
2023.01.13
高齢者のフレイル予防へ。農学部生による健康レシピが商品化

2021.06.21
龍谷大学大学院農学研究科博士後期課程 初の修了生を輩出。3名の有名料亭料理人は大学院でどんな研究をしたのか?(前編)

2018.03.09
料理人、旅に出る!地方の食材から探る日本料理のエッセンス