
連続テレビ小説『おむすび』のヒロインの職業として描かれたことも記憶に新しい、管理栄養士。乳幼児から高齢者までさまざまな人の健康をサポートする、食と栄養のプロフェッショナルなだけでなく、食品メーカーやスポーツ業界などさまざまな分野でも活躍する重要な職業です。
里山が広がり豊かな自然を身近に感じられる瀬田キャンパス。2015年に創設された農学部には、栄養や健康の観点から農作物をとらえ、健やかに生きるための「食」について探求できる食品栄養学科があり、多くの卒業生が管理栄養士として活躍しています。今回は、学生たちを全力でサポートする楠隆教授(国家試験対策委員長)、桝田哲哉教授(副委員長)、鈴木太朗講師(補佐)にお話を伺いました。
編集部/瀬田キャンパスには、給食などの大量調理をシミュレーションできる厨房機器が並ぶオープンキッチンや、植物組織や微生物の「ミクロ」な姿を観察できる顕微鏡室など、最先端の設備が揃っているそうです。充実した環境で、学生たちは日々どのように学んでいるのでしょうか。

「農学部では1、2年生の時に全学科共通で「食の循環実習」を実施します。具体的には、農作物の「生産(栽培・収穫)」から「加工」「流通」「消費」「再生」に至る一連のサイクルを「食の循環」としてとらえ、それぞれのプロセスを体験しながら学びます。土や作物に触れる体験を通じて食の成り立ちを学び、食の循環工程に潜む問題点を顕在化し、互いの関連性を理解することは、将来管理栄養士として栄養指導や食育活動を行う際に必ず活かされると思います。知識だけが先行することなく、お米はどのように栽培されるのか全貌を知り、収穫した目の前の農作物の色や香りの特徴を見て触れて体得することは、食材をどのように加工、調理していくのかを考える上で大切な情報です。自然や地域に根ざした「食の循環実習」での実体験が、今後のさまざまな学びにおいても柔軟な思考を促し、管理栄養士として更なる視野を広げてくれるでしょう。」(桝田)
編集部/幅広い学びの機会が待っている農学部。楠先生、桝田先生、鈴木先生のご専門分野についても、お教えいただけますか。
「私はもともと滋賀県内の小児科医として、特に食物アレルギーによる疾患を専門に診ていました。管理栄養士は医療の分野でも活躍の場がありますので、病院で働く管理栄養士を養成するための基本的な医学知識、そこから発展してさまざまな疾患、疾病を教えています。食物アレルギーはもちろんですし、それ以外にも糖尿病などの生活習慣病や先天性の代謝異常なども、管理栄養士がサポートする対象です。最近は、アレルギーの原因となる食物を完全に避けるという考え方ではなくなってきまして、食べられる範囲で少しずつ摂取し、体が食物を受け付けるように調整していく治療が進んでいます。医師の指導のもと、安全に食べられる範囲を具体的に指導する役割も管理栄養士に求められています」(楠)

「食品学や食品化学が専門分野です。ある食品がどのような成分から構成されているのか、栄養成分がどのような食材に多く含まれているのかを教えています。具体的には、タンパク質や脂質、糖質が化学的にどのような構造をしているのか、味や匂い、色彩や食感に寄与する成分はどのようなものがあるのか、そしてこれら成分の構造や機能が、食品の加工や調理の際にどのように変化していくのかを説明していきます。つまり食品の基礎的な話から加工・調理に至るまで、入口から出口までを網羅する学問です」(桝田)
「私の専門分野は、公衆衛生学とデータサイエンスです。授業としては、栄養、食、健康に関するデータを解析し、「どのような人が、何をどれぐらい食べると病気になりにくく、なりやすいのか」という栄養疫学に必要な、基礎的な統計学を担当しています。最近、管理栄養士の国家試験にも統計関連の問題や計算問題が増えているので、国家試験対策としても活きる講義を意識しています。これからの時代、栄養素に着目した献立を考える上でもデータサイエンスは重要になってきますので、学生の皆さんにはデータや数字感覚をぜひ習得してほしいと思っています」(鈴木)
編集部/食品栄養学科の国家試験の合格率は入学者の90%以上と、全国トップクラスということですが、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。
「基礎学力の違いから、入学してすぐ想像していたより授業が難解でモチベーションが低下し、管理栄養士の資格自体を諦めたいと考える学生もいます。もちろん別の道を進むこともできます。ですが、この学科は管理栄養士の資格を取得することを前提としたカリキュラムを構築しているので、資格を取得しないという選択は、本当にもったいない。今後は、高校でしっかり学んできたかという観点に少しメスを入れ、基礎学力の向上を担っていく取り組みも検討しています」(楠)
「学生が合格したいと本気で思うのであれば、私たちは努力を惜しみません。学習を進めていく中で、思いもよらない壁が立ちはだかることもあるでしょう。そんな時は必ず、解決するために補習などの様々なサポートを提案します。私だけではなく、学科の先生方は非常に親身にスケジュールや学びの進み具合を把握し、学生に負荷が大きくないかを見守りながら、合格までのスキームを常に考えておられます。教員全員が、学生全員の合格のために注力しています」(桝田)

編集部/管理栄養士国家試験そのもののレベルもあがってきていると聞きました。合格率トップレベルをこれからも維持していくために、どのような取り組みが必要だとお考えですか。
「学生全員が合格できるように、下位10~20名ほどを対象とした特別クラスを開講するなど、全員を合格水準まで引き上げる取り組みも考えています。また2023度からは、国家試験を見据えたカリキュラムを3年生の段階から進めています。その一環として、全国管理士養成施設協議会が主催している国家試験を模した栄養士実力認定試験に挑戦することが、良い目標になりました。学部全体で良い成績を目指して取り組んだ結果、大きな成果が得られたと実感しています」(楠)
「栄養士実力認定試験では、受験者全体の1%未満が成績優秀者、5%が成績優良者に認定されるのですが、2024度は優秀者が5名、優良者10名という結果でした。みんな真剣にその試験対策に取り組んだことで、飛躍的に数が増えてきています。成績優秀者は表彰式にも参加しました。また、成績があまり十分でない学生さんにも3年次より補習や助手の先生によるチューター指導を行ったり、教員一同、できる限り管理栄養士を目指す学生さんにサポートしたいと思っています。」(鈴木)
編集部/管理栄養士の資格を取得することで、どんな可能性が広がるのでしょう。
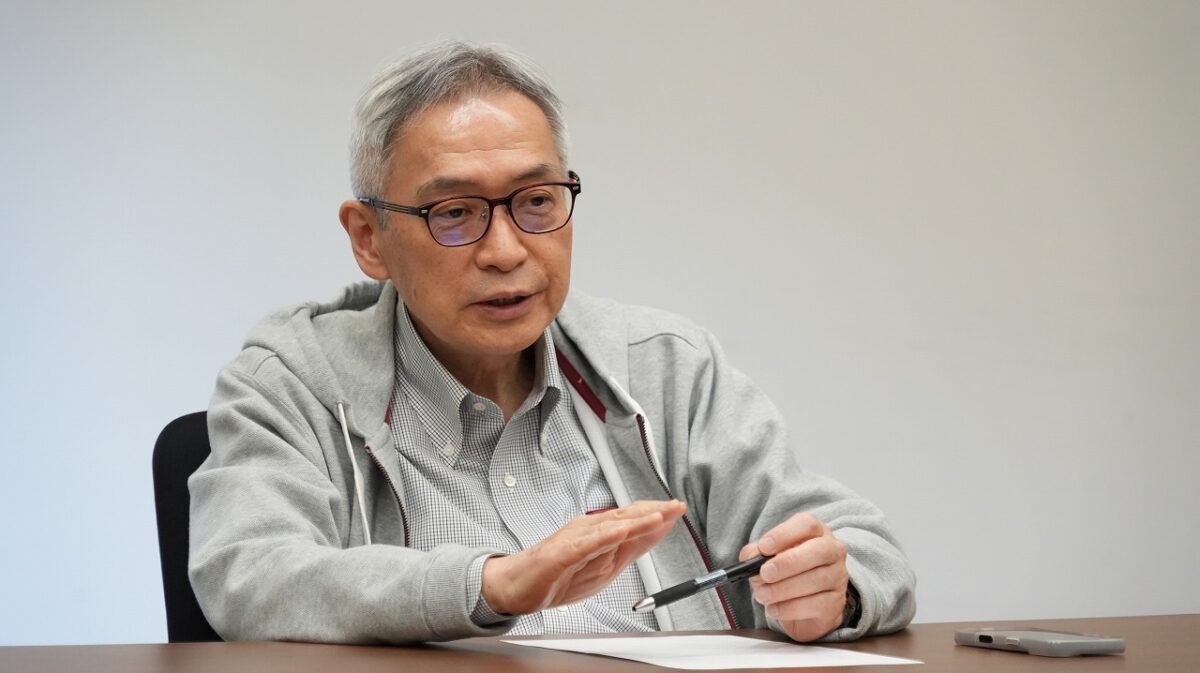
「私は医療の世界から、大学で教育に携わることになりました。一見、異業種のようですが、管理栄養士養成課程には病院の実習があるので、実は管理栄養士は医療とすごく関連があります。となると、やはり人と協調して仕事ができる能力が必要。医師がいて、看護師がいて、薬剤師がいて、管理栄養士がいて…あらゆる職種の人がチームを組んで進める仕事なので、しっかりと協調性を備え、円滑に取り組める人間性も育てられたらと思っています」(楠)
「管理栄養士の実務には、人と人との繋がりを大切にする気持ち、コミュニケーション力がとても大切です。ここ龍谷大学は非常に人との繋がりを重要視する、思いやりを育む環境が整っています。本当に意欲が高く、そして大らかな学生が非常に多いと思います。龍谷大学での新しい出会い、新しい学びに期待してほしいですね」(桝田)
「管理栄養士という職種は、あらゆる分野とつながれます。医療関係、食品メーカー、社員食堂、学校給食の現場、最近ではスポーツ業界でも活躍しています。さらに滋賀県や京都府をはじめとした行政の中で管理栄養士として、地域の健康や食を支えるという仕事もあり、本当にどんな世界にも羽ばたけるのが管理栄養士だと思います」(鈴木)