
2025年3月28日、龍谷大学は環境サステナビリティ学部(仮称)を新設することを発表しました。環境サステナビリティ学部(仮称)は2027年4月、滋賀県大津市にある瀬田キャンパスに開設されます。地域デザイン、ネイチャーポジティブ経営、生物多様性回復、資源循環利用、持続的水質管理といった専門教育プログラムを配置し、環境とテクノロジー、経済・経営にまたがる学びを通じて未来社会を創造する人材育成を養成することを目的とします。
今回は、環境サステナビリティ学部(仮称)の新設発表にちなみ、滋賀県の食にクローズアップ。滋賀県の環境と食の関係を知りながら、滋賀の食文化に親しめる記事を紹介します。
滋賀県は三方が山に囲まれた内陸県。滋賀には美味しい食がたくさんありますが、代表的な食材のひとつが湖魚。琵琶湖はおよそ400万年前に誕生した古代湖で、琵琶湖だけに生息する固有種が66種住んでいます。そのうち固有種の魚は16種で、食用としてはビワマス、ホンモロコのほか、ふなずしに使われるニゴロブナがよく知られています。
滋賀では山や川、県面積の約6分の1を占める琵琶湖といった自然の恵みが、豊かな食文化を育んできました。しかしそのいっぽう、琵琶湖では富栄養化、外来生物の侵入、水質汚染などの環境問題を抱えています。
滋賀の食文化を後世に伝えるには、まずは自然環境を知ること、そしてサステナビリティをめぐる幅広い知識を身につけることが大切です。今回ピックアップしたのは、琵琶湖の「淡水シジミ」、かつて滋賀県で食べられていた「姉川クラゲ」、滋賀県長浜市の郷土料理「鯖そうめん」。滋賀県の自然と環境、そして食文化とのかかわりに触れてみませんか。
▶ピックアップ記事
琵琶湖の淡水シジミがいなくなる!?水温上昇による負の影響を分析(岸本 直之先生)

水質システム工学を専門とする、龍谷大学 先端理工学部 環境科学課程教授(生物多様性学研究センター 兼任研究員)が、琵琶湖の環境と、琵琶湖の固有種である淡水シジミの関係をレポートしました。琵琶湖の淡水シジミは、昭和40年代の最盛期と比べると、現在の漁獲量はわずか1%程度まで減少しているそうです。
そして、滋賀県琵琶湖環境化学研究センターと東レテクノ株式会社、龍谷大学による共同研究で、湖沼温暖化が淡水シジミの生育に負の影響を与えていることをつきとめました。

姉川クラゲはクラゲでもキノコの仲間でもなく、ラン藻類の一種で、「イシクラゲ」とも呼ばれています。滋賀県にある伊吹山の麓(流水地域)では、天ぷら、酢の物などでよく食べられていましたが、現在、食文化は失われてしまいました。
そこで、龍谷大学 農学部4学科の学生・教員が「姉川クラゲプロジェクト」を始動。植物、食材、食文化の研究をおこなったほか、各地のイシクラゲのDNAを分析。さらに、イシクラゲを練り込んだ乾麺の蕎麦「姉川くらげそば」を完成させました。イシクラゲは無味無臭のため蕎麦の風味を損なわず、麺がのびにくくなり温かい蕎麦でもコシが出るのだとか。現在は「姉川くらげそば」の商品化に向けて、イシクラゲの栽培に取り組んでいるそうです。

郷土料理インフルエンサー・谷 草大さんが、滋賀県長浜市での「鯖そうめん」との出会いと、自宅で「鯖そうめん」を再現したレシピをマンガでレポート。「鯖そうめん」は、じっくり煮込んだ焼き鯖とそうめんを炊き合わせた郷土料理です。用意するのは、塩サバ、そうめん、小ネギ、生姜、酒、醤油、みりん、砂糖。
滋賀県長浜市がある湖北地方は、福井から京都へ魚介類を運ぶルート「鯖街道」の途中に位置しており、良質の鯖が手に入りやすかったのだそう。湖北地方には、農家に嫁いだ娘のために田植えの繁忙期に焼き鯖を嫁ぎ先へ贈る「五月見舞い」という風習があります。この焼き鯖を使い、簡単に調理できる料理として「鯖そうめん」は重宝されていたそうです。
マンガに登場する、愛犬(?)ロンの可愛さにも注目です!
▶ピックアップ記事
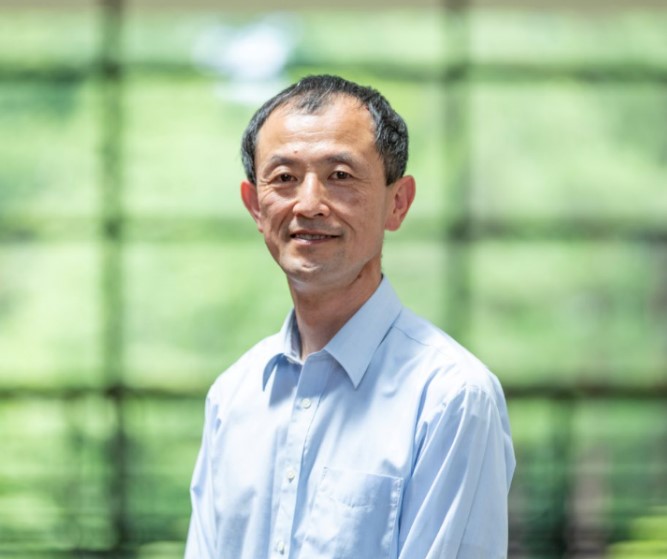
岸本 直之
龍谷大学先端理工学部環境科学課程教授(生物多様性科学研究センター 兼任研究員)
ふっくら大きな殻を持ち、身は肉厚で味わいも抜群と言われる琵琶湖の淡水シジミ。味噌汁の具材はもちろん、しぐれ煮や炊き込みご飯にして、食卓に並んでいた淡水シジミの収穫量が激減しています。昭和40年代の最盛期と比べると、現在の漁獲量はわずか1%程度に。琵琶湖の固有種として親しまれてきた水産資源が、この世から消えつつある原因と対策についてお話しします。
2023年5月公開の『水環境学会誌46巻3号』に、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターと東レテクノ株式会社と龍谷大学が共同研究を進めてきた『琵琶湖産淡水シジミのろ水速度および生育可能条件の評価』の論文が掲載されました。そこで明らかになり話題となったのが、湖沼温暖化が琵琶湖の淡水シジミの生育に与える負の影響です。なぜ琵琶湖の淡水シジミはこれほどまでに、いなくなってしまったのか。その手がかりを掴むため共同研究に用いたのが、培養実験と数理モデルでした。
自然を相手に調査を進める場合、今この瞬間の状況を分析することはできるのですが、対策をした場合と、しなかった場合の結果を比較・分析することが非常に難しいのです。琵琶湖という研究対象はひとつしかありませんから、対策をしてよい結果になったとしても、もしかしたら対策をせずとも良い結果が得られたのかもしれない、とも考えられる。これまでの調査方法では、結局のところ真実がわからない状況でした。
その壁を乗り越えるため、今回の共同研究では、調査や培養実験、分析を統合し、数理モデルとして自然の現状をモデル上に再現しました。数理モデル上の因子を動かすことで、湖沼温暖化が琵琶湖の淡水シジミの生育に与える影響を、客観的に評価することができたのです。月毎の南湖における淡水シジミの成長速度の変化を示したものが、琵琶湖南湖における淡水シジミの成長速度の季節変化(モデルによる予測値)です。ここから読み解けるのは、水温上昇によって夏場の消耗速度が増大するとともに、消耗期間も延長するという結果でした。
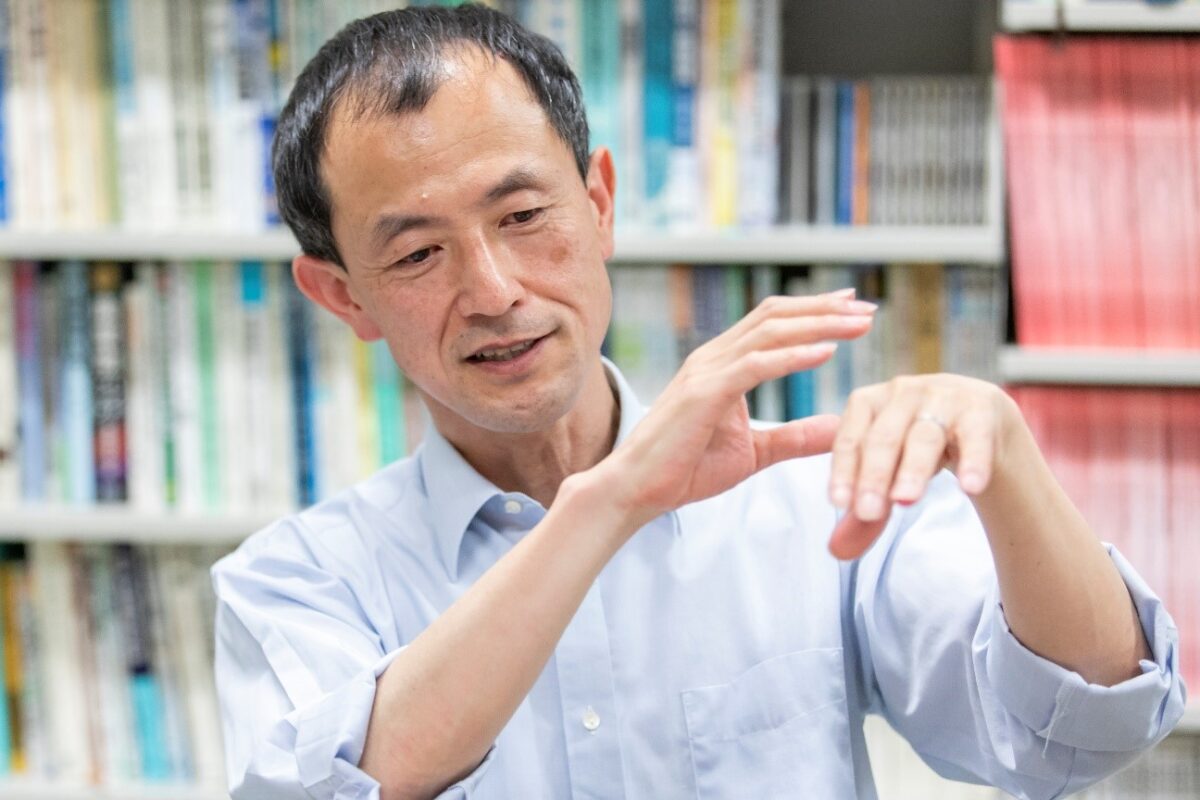
通常、シジミは6月に産卵し、夏という暑く厳しい季節にほとんどが死に絶えます。わずかに生き残ったシジミが秋になって増殖。増殖はしないけれどあまり消耗もしない冬を越え、あたたかい春になるとまたグングン大きくなり、6月に産卵。という過程を繰り返しています。それが水温上昇によって、十分に太れないまま厳しい夏を迎えることになると、夏を乗り越えられないシジミが増えていく。つまりシジミの生存は、確実に困難になると予測できます。もちろん数理モデルには平均的な数値を入力しますので、地域によってばらつきはあると思いますが、水温上昇が壊滅的な結果を導くことは明らかだと考えます。
数理モデルによる評価の結果、水温が1℃上昇するとシジミの成長量は10〜20%程度低下することが予想されます。水温上昇によるシジミ減少を食い止める対策としては、南湖のシジミを水温の低い北湖に移動させること、同じく水温が低い深い水域に生息地を移動させることが必要なのではないかと思います。

さらにシジミの生息地の移動と合わせて、多様な生物が共生できる沿岸域の環境保全をどう進めていくのか、ということも大きな課題です。沿岸域の生物は、湖底に溜まった砂泥の表面に住んでいます。ひと昔前は、人が水草を抜いたり、泥をかき出したりして、やわらかく耕された住みやすい砂泥の状態が保たれていた。しかし、昨今の湖底は人が手を加えず、カチカチに固まった状態です。そうなると生物は潜れないし生息も困難になります。湖底だけでなく砂浜も痩せていく一方で、生物が住めない状況も見られます。
私の専門は「水質システム工学」です。工学とは実学なので、環境問題に対して具体的なアクションを起こすことを重要視し、地域に対してメリットがある結果を導くための手段や方法を模索しています。
水質を含む環境問題の範囲はものすごく広いので、ひとつの技術ですべての問題が解決できるものではありません。世の中に無数にある技術やさまざまな立場の人の力を組み合わせ、問題解決に対応した機能を発現させる。いろんな要素を組織立て、全体で効果を生み出していけるのが「水質システム工学」の魅力だと考えています。
湖底の生物、砂浜の生物を守り、沿岸域の賑わいを取り戻すためには、教育機関と滋賀県との連携はもちろん、住民の方々の協力が不可欠です。住民の方々が保全活動を楽しみながら持続できる、サステナブルなシステムを構築していくことも私たちの役割だと考えています。
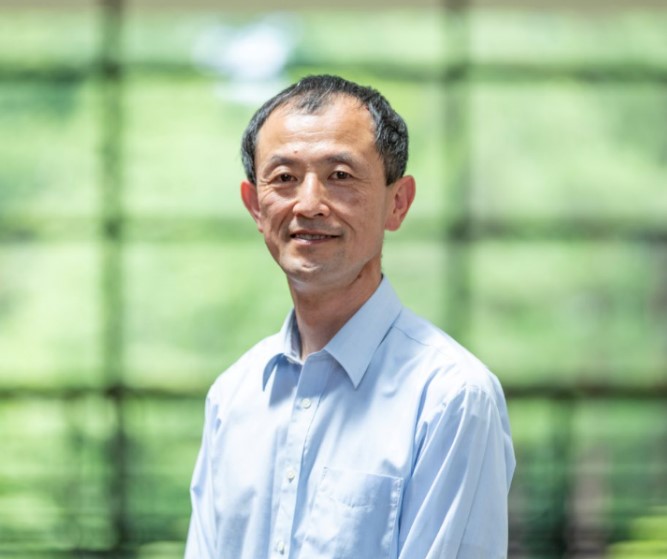
岸本 直之
龍谷大学先端理工学部環境科学課程教授(生物多様性科学研究センター 兼任研究員)
京都大学大学院工学研究科講師、龍谷大学理工学部助教授・教授を経て、2020年より現職。博士(工学)。専門は水質システム工学。排水の促進酸化処理技術や植物プランクトンに関する研究で日本水環境学会論文賞、日本オゾン協会論文賞、WET Excellent Paper Award、日本陸水学会学会賞(吉村賞)など多数受賞している。